鹿大で本気の陸上をやる意味
「最後の青春」を完全燃焼したい!
長距離ブロックの場合(22年8月4日)

国立大学の陸上部で本気の陸上をやる意味とは何だろうか? 前回は短距離の塗木ひかるを取り上げたが、長距離ブロックも近年「全国大会出場」を掲げ、着実に力をつけている。
大学長距離界には「箱根駅伝」というキラーコンテンツが存在するが、関東地区の大学のみしか出場できない大会であり、どれだけ鹿大に強い選手がいて、レベルアップしても出場はかなわない(※24年の第100回大会は全国オープン化が決まっている)。鹿大が目指すのは10月の出雲駅伝と11月の全日本大学駅伝選手権の2つである。2021年12月、今年の出雲駅伝の予選となる九州学生駅伝対校選手権(島原駅伝)で鹿大は2位と躍進した。優勝して出雲駅伝の出場権を得た第一工科大には及ばなかったが、福岡大、日本文理大、鹿屋体大といった強豪校に競り勝っての2位は快挙と呼べるものだった。箱根とは縁がない、陸上に対するモチベーションも様々な鹿大の長距離ブロックの成長の背景にあるものは何であろうか。(※肩書、学年などは22年当時のもの)

そもそも「箱根」を目指せない大学
関東の大学で長距離をやるなら「箱根」という大きな目標がある。高校運動部の部員が「インターハイ」を、高校球児が「甲子園」を目指すのと同じ、もしくはそれ以上の熱量で、4年間を部員全員が同じ方向を向いて取り組みやすい環境がある。箱根のためにその大学を目指した選手たちの集団といっても過言ではない。

鹿大の場合は「駅伝、長距離をやる」ことを第1の目標にして大学に入った部員はほぼいない。現3年生のブロック長・田代敬之=写真上=は日向学院高(宮崎)の出身。高校時代は八百を専門にしていて南九州にまで出場したことはあるが、全国には届かなかった。箱根を目指す大学から勧誘されるレベルではなく、進学は陸上よりも工学部で機械工学を学ぶことをメーンに考えて選んだ進学先が鹿大だった。

藤本悠太郎=写真上=は医学部の2年生。宮崎西高時代は三千障害でインターハイ出場経験がある。筑波大に進学して医学部生として箱根を走るという大きな夢を持っていたが、現役時代は不合格で一浪した。筑波と箱根の2つを目指して受験勉強に励むも、2度目のセンター試験も思うような点数が取れず、箱根の夢を断念して医学部に入ることを優先して鹿大を選んだ。田代とは同い年であり、高校時代から宮崎でともに競い合った友人である。
「鹿大の長距離がこんなにレベルが高いとは思ってもみませんでした」と田代も藤本も言う。長距離ブロックのレベルアップに少なからず貢献したのが、現在工学部の大学院1年の茅野智裕=写真下=だ。
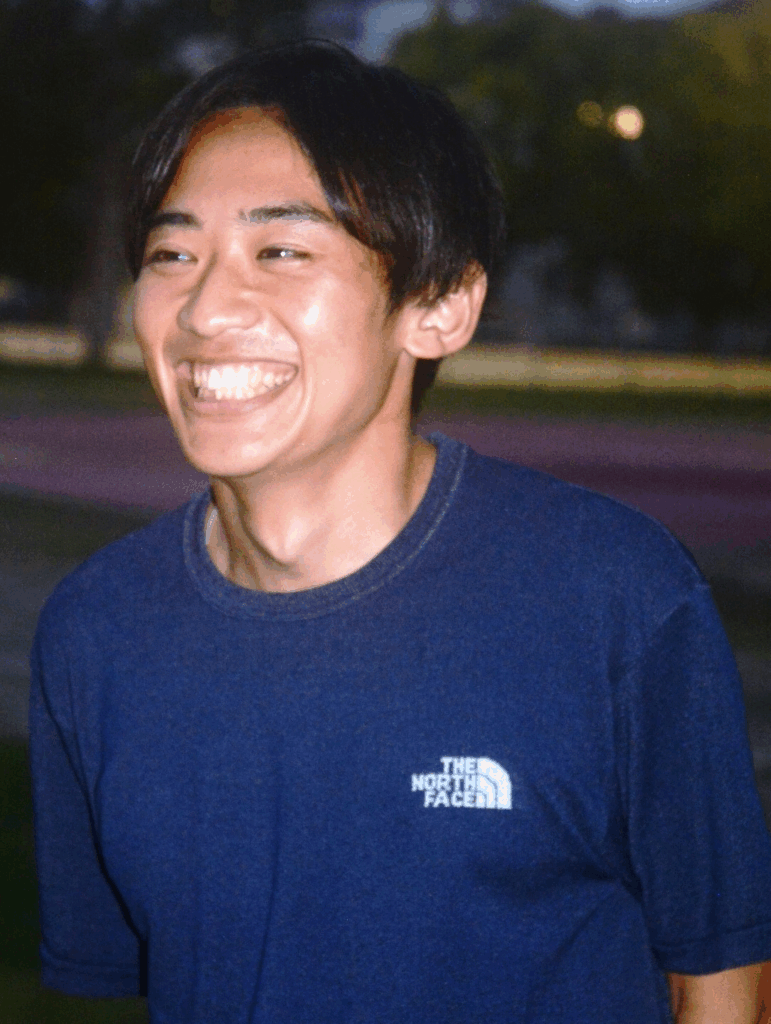
鹿児島工高の出身で、高校時代は全国高校駅伝の出場を目指していたが、故障が多く「1年間まともに走り続けられたことがなかった」。箱根を目指して関東の大学進学をメーン考えていたがが、1つ上の兄が専修大に進学し、その難しさ、大変さも知っていた。「自分が行っても通用しない」という思いが強く、また「高校でやり切った」感もあった。「地元の国立大に行くことが親への恩返し」と考えて鹿大への進学を決めた。「やり切った」感のある陸上だったが、父親が県下一周駅伝の川辺チームの監督をしていたこともあって「県下一周ぐらいは走りたい」と思っていたので陸上部には入った。「大学の駅伝には興味がなく、個人でベスト記録が伸びればいい」ぐらいの感覚だった。予想はしていたが、高校時代に比べて「部活に対する熱量の差があり、受け入れられないものがあった」という。
部活第一、陸上メーンで3年間を過ごした自負がある分、1年生の頃は田代や藤本のように、進学校出身で学業と部活の両立を図りながら競技を続けた他の選手に対して、どこか壁を作っていたようなところがあった。
それでも走るモチベーションになったのは同級生の柴田栗佑の存在だった。兵庫県の滝川高の出身だったが、「自分とは真逆なタイプなのに力があった」のが驚きだった。朝練や補強は全くしないで、夜自分で走っているだけというのに、高校時代から五千で14分台の記録を持っていた。そんな柴田が入学した頃「目標は全日本大学駅伝に出ること」と真剣に語っていた姿を茅野はよく覚えている。当時の鹿大は、全日本どころか九州の予選会にも出場できないレベルだった。そんな柴田に追いつき追い越すことだけを目指して1年生の頃は走っていた。
大きく意識が変わったのは2年生で、塗木淳夫監督から「ブロック長をやらないか?」と依頼されてからだった。当初は就任を渋っていたが、全国を目指せるチームに育てたい塗木監督の情熱に打たれ、「やるからには真剣に全国を目指すチームを作る」意気込みでブロック長を引き受けた。とはいえいきなり全員に「全国を目指す」ことを強制するようなことはしなかったし、できなかった。前述したように鹿大で陸上をやる選手は、それぞれ育ってきた環境も違えば、大学で目指すものも違う。まずは「自己ベストを目指そう」という意識づけからのスタートだった。自身の体験からも「やらされて走る陸上は楽しくない」という信念がある。部員1人1人と対話し、それぞれの陸上に対する考え方や取り組みを「自分と違う」と否定するのではなく「そんな考え方もあるのか」と受け入れる努力をした。

あくまでも「自治」が基本
「集団走で一緒に走っていると、『今、お前が調子いいから〇区を走れるよ』とか『その走りじゃ〇区は難しい』といった会話が自然と出てきます。上級生がそんな雰囲気を作って練習しているおかげで、自分たちもいつの間にか、ここで全国を目指すのが自分の目標として語れるようになりました」。
現ブロック長の田代が言う。例えば関東の私大のように、指導力に長けた「プロ」の監督がいて練習や寮生活を管理するような方式を鹿大はとっていない。監督やコーチはいても、あくまで学生の「自治」で運営するのが陸上部に限らず、鹿大のスポーツ部の伝統のようなところがある。長距離ブロックの練習メニューは茅野からブロック長を引き継いだ田代が決める。全員が集まるポイント練習は週2回。木曜日と日曜日はオフ日と決めているが「オフの日もなるたけグラウンドに行って自分で走るようにしている」と田代は言う。
「本分」の学業も彼らは忙しい。工学部の田代は「実験があって毎週10枚、手書きでレポート書く」ようなことが当たり前にある。朝練を走って学校に行って、授業を受け、放課後に練習。アルバイトで酒屋の配達もしている。医学部の藤本は「朝9時から夕方6時まで解剖実習」のようなスケジュールがざらにある。キャンパスも他部と違って桜丘にあるので、ポイント練習以外の日は自分で走っている。塾講師のアルバイトもしている。学業、陸上、アルバイトでほぼ日々のスケジュールが埋まるタイトな生活だ。そんな中でも「全国を目指す」気持ちでいられるのは「この仲間となら全国も夢ではない」という想いがあると田代は言う。五千のベストが13分台、一万のベストが30分を切るような「スーパースター」はいないが、志の高い仲間たちが持てる力を結集すれば、全国に行けるのではないか。そう思わせてくれたのが昨年の島原駅伝の2位だった。
最後の青春を完全燃焼!
「元々、二兎を追って二兎を得たい性格でした」と藤本は言う。高校時代も学業での「医学部合格」と「インターハイ出場」を追いかけて、一浪はしたが、どちらも夢を叶えた。筑波大で箱根を走る夢は断念したが、鹿大で全国に行くのはそれと同じもしくはそれ以上に価値のある夢だと思える。高校時代、三千障害でインターハイには出たが、東京五輪に出場した三浦龍司(順天堂大)と同じ組で予選を走り「周回差つけられそうになった」ほどのレベルの差を見せつけられた。高校の頃は駅伝で全国を目指せるレベルの学校ではなかった分、個人種目に絞っていたが、今は駅伝でも、そして個人でもあわよくばインカレ出場と高い目標を自身に課している。インカレの標準記録は9分1秒。今のベスト記録は9分4秒で十分射程圏にある。学業との兼ね合いでチーム練習にはフルで参加できないが「自分のせいで足を引っ張ることはしたくない」気持ちがモチベーションになっている。
茅野は高校時代とは違う感覚で陸上に取り組み、2年間ブロック長を経験したことで、人間の幅が広がった。「鹿児島に残っているのが大きいのかもしれません。高校時代、お世話になった東村(光弘)先生に恩返しをするつもりで今陸上に取り組んでいる」という。
今年の全日本大学駅伝の出場を争う予選会が6月19日にあった。こちらは島原駅伝のように駅伝を走るのではなく、競技場のトラックで一万を走り、エントリーした8人の合計タイムで争う。鹿大は3位。2位の福岡大とは約4分、優勝した第一工科大とは約10分の差がついた。8人全員がベストコンディションで臨むのが難しく、故障明けの選手や経験の浅い1年生が走ったが、一工大とはレベルの差を痛感させられ、福大には昨年の島原駅伝のリベンジを許した。

「厳しさの差かもしれない」と茅野は言う。留学生を擁し九州の盟主を自認する一工大、関東の私大並みに環境が整い、高いレベルでまとまっている福大、こういったライバルたちに勝って全国に行く難しさを改めて痛感させられた。鹿大で全国に行く。青臭い夢に聞こえるかもしれないが「最後の青春を完全燃焼したいですから」と田代は言う。自分たちが30代、40代、年齢を重ねて大人になったとき「自分の青春は駅伝だった」と胸を張れるものが欲しい。そのために必要なのが「全国大会出場」という「勲章」だと田代は考えている。
※注 鹿児島大は23年、24年と2年連続で見事、全日本大学駅伝の出場権を獲得した。
