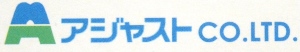子どもたちの所属するバレーボール少年団の夏休みのイベントで、鹿児島市にあるふるさと考古歴史館に足を運んだ。「火起こし体験」をするのが最大の目玉だった◆「まいぎり式」と呼ばれる最も原始的な火起こし方法で、弓矢のように先のとがった棒と板を使う。摩擦を利用して、火種を作り、それを燃えやすいものに移して、火を燃やす。子どもたちは2人1組になり、安全面には大人が最大限の注意を払いながら、自分たちで火を起こすことを心から楽しんでいた◆マッチ、ライター、着火マン…今や「火をつける」こと自体は何でもない簡単なことだが、太古の昔、最初に火を起こすことを思いつき、前述したような道具を使用すれば火がつくと「発明」した人はどんな発想の持ち主だったのだろう。想像するだけでも、畏敬の念を感じずにはいられない◆どんなことがきっかけで、どんな人が思いついたのかは、今となっては分からない。火を燃やす。その方法を思いついた人間がいたことで、人類の文化は長足の進歩を遂げた。まずは、暗闇を照らす明かりができた。日が暮れれば眠るだけだった生活に、明かりを灯す習慣ができた。自然のままにあるものを食していただけだったのが、火を通して調理する発想が生まれた。身を守るための武器もできた。こちらは今の軍拡時代を思うと、負の遺産といえるのかもしれない。いずれにしても、人類の進歩の歴史を身近に感じた貴重な体験だった。