「鹿児島のバスケット」にこだわる!

「鹿児島のバスケット」にこだわり続けた理由は、突き詰めれば、鹿児島からメジャー大会の「日本一」を出したいという想いです。「そんなことできるものか」「県外に出ないと無理」といった考え方が大嫌いでした。県外のレベルが高いというのは絵空事。例えば福岡県は母数が多いので、確かにレベルの高い選手は多いですが、何といっても福岡第一高と福大大濠高のレベルが抜きん出ている。これは2つの学校の「企業努力」が実ったのであって、イコール福岡全体のレベルが高いこととは結び付かない。そういうチームがない鹿児島としては、企業努力を県全体でやるしかないという発想です。
「日本一」を目指す原点

日本一を目指したいと思った原点は甲東中時代の恩師だった織田文雄先生=写真上=です。太陽国体の強化指定選手で、とにかく命がけで練習をしていた。当時、自分は運動が全然できなかった。できないから練習する喜びを教えてもらった。運動能力のある人は、自分ができる反面、教えることはあまりうまくない。でも織田先生は運動ができない人にも懇切丁寧に教えてくれる。恥をかくことの素晴らしさを教えてくれました。
出身は宮崎ですが、鹿児島大に進学、鹿児島国体の強化選手として日本一を目指していた。その姿が自分に映っています。練習はとにかく厳しかったから心肺機能だけは発達する。運動は苦手だったはずなのに、気づいたら体育祭の長距離選手に選ばれていました。
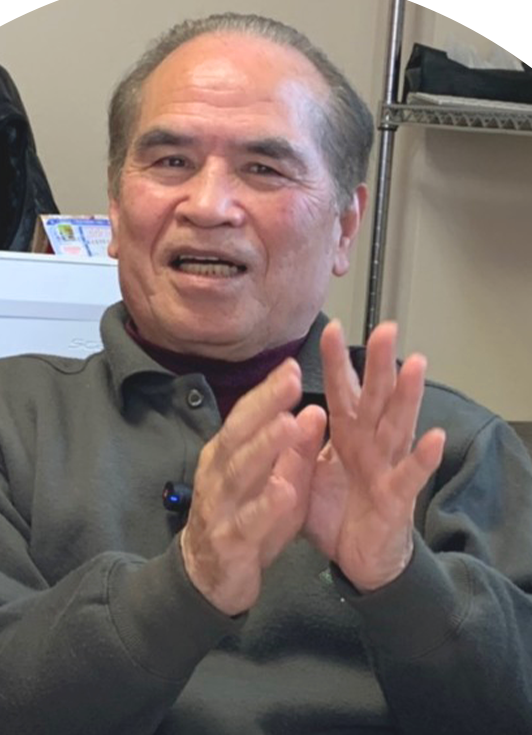
吉川覚先生=写真上=は、オンコートで「成功する」とまず決める。メジャーリーガーの大谷選手のようですが、まだどうなるかもわからない中学生を前に「おめでとう、君たちは九州チャンピオンだ」と宣言してからチームを作っていった。それがかつて古田仁さんらがいた頃で、現在までに唯一九州大会を優勝した中学男子チーム、1981年の伊敷中です。女子の指導者で亡くなられた平瀬弘雄先生は職人気質の先生でした。そういう人たちを見てきて、影響を受けました。
エネルギーの源
教員チームで活動していた頃、80年代の前半でしょうか。当時の日本リーグの試合を見ても、響くものがなかった。テレビのカメラも入っている実業団チーム同士が日本一を争う試合のハーフタイムでも平気でたばこを吸っていた。そんな時代でした。鹿児島で実業団の試合があった時、協会経由で依頼を受け、教員チームがオフィシャルで入っていたので、そういった選手たちの様子が手に取るように分かる。レフリーに文句ばっかり言って「やってられないよ、こんなんじゃ!」と監督が平気で言う。「こいつら、やつけようよ」とエネルギーになりました。
そんな時に、指導者として鮮烈な印象だったのが中村和雄さんです。そののちの指導者が皆影響を受けています。亡くなられた佐藤久夫先生、富樫英樹先生、福岡第一の井手口孝先生。鶴鳴学園の山崎純男先生も、素晴らしい先生で、そのち密さを大いに学びました。女子の指導者を中心に「学びたい」と思う指導者が次々と出てきて影響を受けました。織田先生や吉川先生のように、上を目指すことが当たり前だった先生たちから受けた影響は大きかった。人と同じことをやっていても勝てないという想いが強烈にあった。

今、レブナイズは山崎俊オーナー=写真上=の下、単なるバスケットを超えて、スポーツを切り口にした地方創生をやりたいという夢には大いに共感します。一方で、今いるレブナイズの選手たちのレベルの高さ、フェルナンド・カレロ・ヒルHCのニューヨークの洗練されたビジネスマンのように計算しつくされたバスケットを見ていると、私がHCだった頃のレブナイズ、大きな外国籍選手もいない面子でどうやって勝とうか、コーチ目線で考えている自分もいます。「勝ちたい」というのは長年コーチをやってきた人間の性のようなものです。創意工夫の限界も知っているけれど、何とかできるはずだという可能性を常に考えている。そういうことを考えていると、いろんなアイディアを出してやらざるを得ないからそうなっていくのだと思います。
「渦を巻く」という発想
92年の山形国体は、私が成年男子に関わるようになってからの初勝利なら高知国体はベスト8入りして初めて得点を獲得した節目の大会でした。02年は松崎浩隆先生に監督をお願いしていました。宮迫崇文先生たちがプレーヤーとして全盛期の頃です。00年の富山国体は山元晃一先生に監督をお願いしました。私自身が監督をやりたい気持ちはあるのですが、私以外の色んな人がそういった舞台を経験し、勉強したり、成功感をもってもらうようにすることが指導者のすそ野を広げることにつながる。特に計算しているわけではないのですが、今でもやっているようなことは昔から普通にやっていましたね。
それこそ渦を巻くという発想です。小さなところから少しずつ、色んな人を巻き込んでいく。自ら切り開いたのが山形で、プロデューサー的な立場で得点まで獲得したのが高知ということです。
鹿児島高専でやっているときに、まだインターハイなどメジャーな大会に出られなかった頃、森山恭行先生という松江高専のすごい指導者と出会って、そこでいろんなことを教えたり、実験することができた。教員チームの場合は離島からも出てくる先生がいるので月に2、3回しか練習ができない。学生の後ろにくっついてやると効率が良いのです。教員チームが高専とくっついてやっていたように、その方式は今でも続いています。今のレブナイズのセカンドチームであるレッドモンスターズ(RM)はレブナイズの永久欠番である松崎圭介君がヘッドコーチとなり、第一工科大学の学生が一緒にやってもらっている。
教員は教えるのが仕事。こっちがいろんなアイディアを出すと良いものを学生たちもが取り入れる。教員、学生、双方の「相乗効果」も期待できるというわけです。こういう発想もいろんなものを巻き込んでいく「渦」の発想ですね。
「必然の世界」に落とし込む

私自身はプレッシャーに弱い(笑)。BリーグでレブナイズのHCをしているときも試合が始まるまで、すごく逃げたい。チャンピオンシップがかかった県の代表などは他の人がしてくれた方がいいと思うのです。逃げて、逃げて、逃げて、気が弱い。ヒリヒリした世界にいる自信がない。でもやっている。
そこまで突き詰めているのは大なり小なり、どの指導者にもあるのではないでしょうか? 相手のアップを見ながら、何かのアクシデントが起こって2、3人ケガしてくれないかなと思うこともある(苦笑)。リングに蓋がしてあってシュートが全く入らないのではないかと怖くなる。バスケットって実はそういう競技でもあるのです。ネガティブ、マイナスなことへの想像力はどうしても止められない。少しでも楽になるためには、全てを背負いつつ、どうすればいいかを考えて、一つ一つ消していくしかない。
試合が始まると、楽勝で勝つ試合はほとんどないので、どうする、どうすると突き詰め、我慢しながら、戦っていく。気合いだとか、気持ちの世界に逃げることは200%ないです。偶然に身をゆだねず、全てを必然の世界に落とし込む。それでも偶然に支配されることがあるからスポーツは面白い。
レッドシャークス時代にやったこと

そういう発想の中から、鹿児島に韓国の延世大学を呼んで試合をするとか、香港である国際大会に出るという発想が生まれたものです。中国人のチン・ハイモ選手がレッドシャークス(RS)の選手として来てくれたり、アメリカ人のジョン・パトリックさんによる指導も実現したわけです。
「外国人がRSを教えている」という絵が欲しいとふと思ったことがありました。それができるのはジョンさんしかいないと思って、引き受けてもらいました。その前には今、東海大の監督をしている陸川章さんにも来てもらいました。日本鋼管でプレーヤーを引退するときに、彼と親しい上大田信也先生を通じて、引退ゲームのその日に「RSでプレーしないか?」と口説きに行きました。プレーヤーとして来てもらうことは叶いませんでしたが、「自分の持っているものを伝えたい」ということで、1年間定期的に教えに来てもらうことが実現しました。

そういった縁があって、RSでプレーした白澤広宇君とか、レノヴァでプレーした西堂雅彦君らが鹿児島に戻ってくるきっかけにもなりました。(後編に続く)
